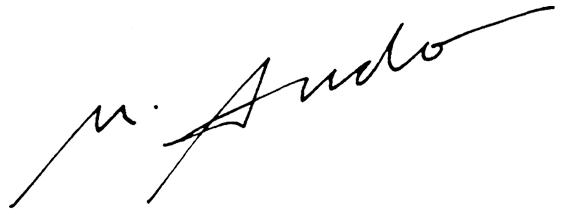Shaping the Void | 余白を形づくる

現代美術作家を目指し、1985年初めてニューヨークを訪れた。その時近代美術館の日本コーナーに、民藝作品・根付・北大路魯山人の工芸作品が展示してあった。それを見た時、肩肘張って美術を学び、背伸びしてきたことから少し解放されたような気がした。日本人にとって美術とは何だろうと考え始めていたので、そこに二つの意味を見出した。ひとつは日本を代表する美術として純粋美術ではなく工芸が選ばれていたこと、もうひとつは工芸の中でも鑑賞工芸ではなく実用工芸であったことである。

百数十年前、日本は鎖国から開国して以来、西洋文明を取り入れる一方、鑑賞工芸を輸出していた。世界に誇れる文化芸術として美術作品に負けない鑑賞工芸の制作を推奨し権威化もした。日本が取り入れた西洋美術の概念には純粋美術が上、工芸は下というヒエラルキーがあり、工芸が国を代表する文化とされていたのに下に据え置かれていることで、ねじれた文化構造になってしまったのである。それ以来、工芸は美術に対抗意識を燃やし、本来の工芸、つまり実用工芸の姿を忘れかけていた。

焼物に携わり始めた時から僕はそのことに違和感を持っていた。鑑賞工芸のような権威化も上昇志向も持たず、日本人として自然に出来る自己表現を目的としない普段使いの器と彫刻を制作したいと考えるようになった。高級化した陶芸作品と日常使いの工業製品の間がぽっかり空いており、日々の暮らしで使いたいと思える手仕事の器がないという枯渇感を覚えていたので20世紀の終わり頃から作り始めた。

同時期に日本では様々な素材の作家で同好の士が現れ、後に生活工芸と呼ばれるようになった。生活工芸と同じようなカテゴリーもなく、上下の区別もない新しい価値観が21世紀に世界で同時に生まれ広がっていると感じている。目指しているのは、環境に優しく、持続可能であり、作り手・使い手・売り手など携わる人々が幸福を得るものである。制作的には過剰な装飾を抑え、使う側に様々な使い道を喚起させる余白のある器であり彫刻である。

同じ器でも料理によって、また盛り付けによって全く別の器に見えることがある。人の身体が何らかの形で作品と交わることで、見えなかったものが見えてくる、気付かなかったことに気付く、それをアートと定義するならば、美術と工芸を分け隔てるものは何も無い。器と彫刻が共に持つ空間の形に、創造を膨らませて欲しいと願っている。
安藤雅信